
能登といえば、日本を代表する酒どころとあって、
“能登”と“ワイン”の組み合わせに、少し違和感を覚える人もいるかもしれません。
この小さなワイナリーがワインづくりを始めたのは、たった6年前の2006年のこと。
それからわずか数年、国産ワインコンクールで4年連続の入賞を果たすなど、
全国のワイン愛好者から大きな注目を集めるほどの飛躍を見せています。
能登穴水の小さなワイナリー「能登ワイン」の挑戦は、
まったく何もないところからスタートしました。
能登空港の開港を機に、能登の新しい特産品を生み出そうと、
地元産の葡萄にこだわったワイン製造を志します。
まずワイン用葡萄品種の苗木栽培から始まり、
赤土だった畑にミネラル豊富な牡蠣貝を混ぜ込むなどして土壌を改良、
そして葡萄を襲う数々の病気との戦い……。まさに試行錯誤の連続です。
通常、このようにワイン専用種の葡萄をいちから栽培した場合、
本格的な収穫まで5年はかかるとされているのですが、
それにも関わらず、まだ歴史の浅いこのワイナリーが高い評価を受けるのには、
やはりさまざまな理由がありました。
能登ワインの川端さんは、軽妙な語り口で
ワインづくりのこだわりを次のように話します。
「能登ワインに使用される葡萄はすべてハサミで収穫しています。
枝の剪定も葉摘み作業もすべてが手作業。
海外などでは効率化のために機械を使うことがほとんどですが、
我々はワインづくりに適した葡萄をきちんと人の手で選り分けることが
上質なワインづくりにつながると信じています。ですから、
常にていねいな仕事を心がけているんです」
その他にも、コルクには天然のものを使用したり、
キャップシールにナイロン系のものでなく錫素材を使用したりと、
細部にまでこだわり、ワインづくりと真摯に向き合っています。
「まずは、多くの方に『能登ワイン』を飲んでいただきたい。
とにかくその一心です。飲んでいただかなければ何も始まりませんから。
さあ、まずは私たちのワインづくりの現場をご覧ください」
そう言いながら工場の中をくまなく案内してくださる川端さん。
工場見学ツアーのスタートです。

能登ワインの大きな特徴は、
「能登産の葡萄が原料」「加熱処理を施さない生ワイン」
という点が挙げられます。
特に“生ワイン”の製造は国内に於いて大変珍しく、国内90%以上のワイナリーでは
加熱処理したワインがつくられていることからも、その希少さが伺えます。
「欧米などのヴィンテージワインは、すべてが“生ワイン”。
年月を重ねるごとに瓶の中で熟成が進み、
ワインの味がさまざまな表情へと移ろいでいくのが最大の特徴です」。
川端さんはそのように生ワインの魅力を語ります。
ちなみに、“生ワイン”とそうでないワインの見分け方は、一目瞭然。
ワインボトルの底が内側に盛り上がっていたら、それは“生ワイン”の証です。
グラスに注いだときに、熟成の過程で発生した
ワインのダイヤモンドと呼ばれる澱(酒石)が引っかかるように、
そのような形状になっているのです。

工場内に並ぶ巨大な熟成タンク。
徹底した温度管理に始まり、
熟成の際に発生したガスを抜くなどの作業が行われています。
ちなみに、こちらは1万リットルタンク。
このタンク1本から約1万3000本のワインがつくられます。

ヴィンテージワインの樽を貯蔵する蔵の中は、
ひんやりとした不思議な空間。
樽で熟成させる期間は銘柄によっても異なりますが、
例えば、国産ワインコンクールで銀賞を受賞している
「クオネスヤマソーヴィニョン」の場合は、
約14カ月の樽熟期間を経て、フルボディータイプの赤ワインへと味を変えていきます。

試飲用の樽。
赤ワインの色素で樽が真っ赤に染まっています。
こちらのワイナリーで使用される樽は、
アメリカンオークとフレンチオークの二種類。
日本で言うところの樫の木で、船などに使われる木材です。
樽で熟成したワインは、程よい樽香が付き、
年月と共に味わいが増していきます。

能登ワインの葡萄果皮でつくった
「能登のもったいないジェラート」(90ml、262円)。
ワインの製造過程で出される葡萄の果皮は、一年で約10トンほど。
この商品ができる以前は、すべて廃棄されていましたが、
葡萄の皮にはポリフェノールや酵素など、身体に良いとされる成分が
多分に含まれているため、どうにか有効活用していこうと、
「もったいない葡萄プロジェクト」によって商品化されました。
ワイン風味のちょっと大人のジェラートです。
※金額は2016年6月27日現在のものです

ギャラリーには、試飲コーナーも。
国産ワインコンクールで銅賞を獲得した「心の雫」(赤)、
同じく銅賞の「マスカットベリーA」(ロゼ)、
奨励賞の「ヤマソーヴィニョン」(赤)など、多くの銘柄を試すことができます。
長期の熟成が必要なワインや、若い間に楽しむワインなど、
いろいろ試して、自分の好みを見つけてみてください。
「一般的に肉料理には赤ワイン、魚料理には白ワインと言われますが、
そういった常識には縛られずに、最後は結局、自分の好きな味でいいんです。
それに、日本の赤ワインは柔らかい口あたりのものが多いので、和食にだって
良く合うんですよ」と、店員さんがさまざまなアドバイスをしてくれます。

取材時に工場を案内してくれた能登ワインの川端さん。
「ワインはあくまで脇役で、皆さんの会話や食事が主役です。
ワインはその側にいることで、主役を引き立て、
周りの人々を笑顔にすることができる。ワインにはそういう力があります。
私自身、もちろんワインも好きですが、とにかく人が好きなんです。
人の笑顔のために、これからも能登ワインを提供し続けていきたいと思っています」
ギャラリーや工場見学(団体は要予約)のほかにも、
事前に連絡をすれば葡萄畑での簡単な作業も体験できます。
また、能登ワイン友の会「和飲会」に入会すると、
能登ワインの定期配送(年間8本)、葡萄収穫体験、試飲会、
限定品の優先購入などの特典が受けられますので、
能登ワインに惹かれた方は、ぜひご入会を。
このお店に行く
多田屋から車で80分
〒927-0006
石川県鳳珠郡穴水町旭ヶ丘り5番1
- TEL:
- 0768-58-1577
- 営業時間:
- 9:00~17:00




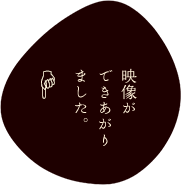
能登でワインを作る。それを実現するまでの努力はいかほどだったか。そして今でも実直に、益々美味しいワイン作りを続けている。ぜひ工房にも訪れて欲しい。そのワインの種類の多さと、工房の方々の熱意に、きっと工房を出る頃には笑顔でワインを買っているはずだ。