
400年以上の歴史を持つ「揚げ浜式製塩」。
白米千枚田などとともに「世界農業遺産」に登録されており、
国の重要無形民俗文化財にも指定されている能登の伝統文化です。
これは江戸時代以前より続く製塩法で、
汲み揚げた海水を砂浜の「塩田」に何度もまき、太陽と風の力で蒸発させます。
そして塩がついた砂に海水を注ぎ、塩分濃度の高い水を作り、
それを釜で炊いて水分を蒸発させて塩を作ります。
こうして時間と手間をかけて行われる天然の製塩法は、
能登が世界農業遺産に選ばれた理由のひとつでもあります。
「しおサイダー」などのヒットによって注目を集めるこの伝統文化を、
奥能登塩田村で体験してきました!

石川県の「ふるさとの匠・伝統の匠」に認定されている浜士(はまじ)・登谷良一さん。
浜士とは、製塩に従事する技術者のこと。
「浜」に「サムライ」と書いて浜士。カッコイイですね。
登谷さんが海水をまく姿はさすがの迫力。
水が美しい弧を描いて、砂にまんべんなく散ります。

というわけで、奥能登塩田村の登谷さんに伝統の揚げ浜式製塩法を教えてもらいました!
ちなみに5月1日〜9月30日の期間は、
予約すれば誰でも塩づくりの体験学習ができます。

奥能登塩田村には、元気な女性陣もいます!

まずは塩づくりの原料となる海水を汲みに行くところから。
ひとつ36リットルの海水が入る「かえ桶」を、
「肩荷棒」という桐の丸棒を使って担ぎます。
でもこれ、空の桶でも相当重い!

塩田の目の前には、美しい日本海が広がります。
しかし、バランスをとりながら海水を汲み揚げる作業もひと苦労!

汲み揚げる海水の量は、1回あたりナント72リットル。
重さにして60kg以上!
多い時期には630リットル以上の海水を繰り返し汲み揚げます。

汲んできた海水は、塩田の真ん中に置かれた「しこけ」と呼ばれる
大きな桶に集められます。

「しこけ」にためた海水を、
「おちょけ」という小さな桶ですくって塩田にまんべんなく撒いていきます。
水が均一に行き渡るよう、弧を描くように撒いて…

最後に「クッ!」とひとひねり。
空にしぶきを舞い上げます。
しかし、これがけっこう難しい作業で、
浜士さんのようにキレイな孤を描き、かつ霧状にまんべんなく撒けるようになるまで、
ナント10年以上はかかる技術だとか。
ちなみに揚げ浜式製塩は、雨天時には製塩できず、
潮まきの決行は、水平線の見え方や雲の様子など、
浜士の長年の勘で天候を予測した上で判断されます。

海水が乾いたら、塩田中央にある「たれ舟」という集積所まで
数人で手分けして砂を集めます。
女性には重労働ですが、さすがは達人。
軽快にどんどんかき集めていきます。

砂を集める道具は「いぶり」といいます。
押し出すのではなく、手前に引いて使います。
けっこうな重さです!

「いぶり」の操り方を優しく教えてくれる登谷さん。
そして、野球部時代に鍛えたトンボがけの技術をいかんなく発揮する多田健太郎。

砂を集めた場所に、板を組み立てて「沼井(ぬい)」と呼ばれる箱を作ります。
縄で締め上げて固定するため、かなり力のいる作業になります。

「沼井」の底にむしろを敷き、かき集めた砂をすくって入れます。
このとき使用するのが、「しっぱつ」というスコップのような道具。
こちらも腰にくる重労働です…。

真夏の海辺はとても暑いので、
塩田での作業は、少し湿り気のあるひんやりした砂を裸足で踏みしめながら行います。
そのため、凹凸のある砂の上で踏ん張る脚力も必要なのです。

集められた砂の上にむしろを敷き、海水を注ぎます。
「沼井」の底には目皿が張られており、
塩分濃度の高い「カン砂」を通過しながら海水がゆっくりろ過され、
底の穴からさらに塩分濃度の高い「かん水」が流れ出てきます。

「かん水」をペロリ!
塩分濃度は海水の約5倍もあり、かなりしょっぱ〜い味。
明治以降は濃度計で計っていますが、江戸時代は熟練による勘が頼りで、
これも「浜士」の腕の見せ所だったとか。

できあがった「かん水」は、約600リットルも入る釜に移され、
まずは薪で6時間ほど炊きあげられます。
これは「荒炊き」と呼ばれる作業で、一度ゴミや不純物が取り除かれた後、
今度は17時間の「本炊き」に入ります。
ここからはやわらかい炎でじっくり炊きあげるため、燃料にはわらが用いられます。

「かん水」を煮詰めると、結晶化した塩が浮き上がってきます。
この表面の塩を集め、4〜5日放置してにがりを抜けば、
ついに奥能登名物「揚げ浜塩」の完成です。
ちなみにこれ、1,080リットルのかん水からとれる量がたったの180kgという、
非常に希少な塩なのです。
奥能登塩田村では、そんな塩を使った様々な商品を販売しています。
(左から)
・結晶の形が非常に美しく、ほんのりした甘みをたたえる「奥能登揚げ浜塩」。
550円(100mg)、1,550円(300mg)
・揚げ浜塩にオレガノやバジル、パセリなどを混ぜた無添加の「ハーブじお」。
700円(40g)
・丹念に焼き上げて水分を飛ばし、ふりかけやすく仕上げた「焼塩」。
900円(70g)
・能登名産の魚醤「いしる」味に仕上げ、コクと深みを増した無添加の「いしるじお」。
1,000円(70g)
※2016年6月27日現在

ここ奥能登塩田村の職員たちと、
外部スタッフとのコラボレーションで生まれた「しおサイダー」。
発売1年で25万本を売り上げた、能登を代表するヒット商品です。
1本(340ml)200円、6本セット・化粧箱入り1,300円
※2016年6月27日現在

奥能登塩田村は、日本海に面した抜群のロケーション!
塩づくりを体験した後、水の澄んだ磯を歩き回るのも楽しい。
また、塩の歴史や文化を学べる「塩の資料館」も併設しているので、
塩のことを深く知ることも!
日本で唯一の揚げ浜式製塩を、
壮大な日本海を眺めながら体験できる奥能登塩田村に、
ぜひ足を運んでみてください。
ここに行く
多田屋から車で135分
〒927-1324
石川県珠洲市清水町1-58-1
- TEL:
- 0768-87-2040
- 体験学習
- 14:00~16:00、所要時間90分
※5月1日~9月30日まで、要予約
※一人500円~3,500円 - 塩の
資料館 - 09:00~17:00、入館は16:30まで。通年営業
※大人100円、小・中学生50円 ※2016年6月27日現在
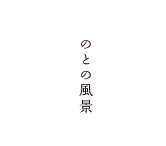






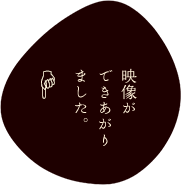
昔ながらの方法で、海からの恵みを取り出す。言葉にすると簡単だけど、いざその仕事をやってみると控え目にいってすごく大変。力も技術もいる。天候にも左右される。自然の力でつくりあげる塩田村の塩が美味しい理由がわかったし、能登にそんな素敵な文化が残っている事に感謝。