株式会社佐々波鰤網/漁師
大畠 要さん(おおばたけ かなめさん)
能登に古くから伝わり、
自然に優しく、魚の鮮度にも優れた漁法として知られる「定置網漁」。
そこで捕れる寒ブリなどは、秋〜冬にかけて食べ頃を迎える能登の風物詩といえます。
そんな定置網漁を若き副船頭として牽引する漁師の大畠要さんに、
漁業の現在や能登の食文化について
多田健太郎が話をうかがいました!
世界遺産の里海を支える“待ち”の漁法

七尾の「定置網漁」は、一説には戦国時代の末期から始まったと言われるほど、非常に古い歴史を持つ伝統漁法です。1579年には、かの織田信長にもブリを献上した記録が残っており、この漁法は七尾が発祥の地のひとつとされています。
「定置網漁とは、“捕る”よりも“待つ”というイメージの漁法です。ずっと同じ場所に仕掛けてある網に魚が入るのを待ち、それを引き上げるというやり方なのですが、乱獲をして生態系を崩すことがないため、自然に優しい漁法と言われています」
世界農業遺産に認定された能登の「里海」とは、「人の暮らしと自然の営みが密接な沿岸地域」と定義されていますが、それを支えるのがこの定置網漁。自然のバランスを壊すことなく恵みを享受するという、里海を形成する上で欠かせない漁法なのです。
「網の内部はちょっとした迷路のような構造になっていて、回遊しながら進んでいく魚の習性を利用し、奥の方へと誘い込みます。奥に行くほど編み目が細かくなっていくのですが、体の小さな稚魚などは、途中で大きな編み目から外に出ていきます。こうして魚の育成を守り、資源の保全を行っています」
魚は貴重な資源であるという意識を徹底させ、管理と育成を行いながらその恵みをいただく。定置網漁は、まさに里海ならではの漁法と言えるでしょう。

父の背中に憧れ、厳しい漁師の世界へ

漁師の仕事というと、船の上から魚を釣り上げる姿をイメージするかもしれません。しかしこの定置網漁は、50人以上の漁師が連携しながら網を引き上げる“チームプレー”の漁。その迫力はまさに圧巻です。
「海に仕掛けてある網を、3艘の船で連携しながら引き上げていきます。大がかりな作業なので、若手からベテランまで、ほぼ会社総出の50人体制で臨みます。ロープひとつ結び間違えたら船が離れてしまうし、引き上げにモタつくと、網やロープに足が絡まって海へ引っぱられてしまうこともあります。海が荒れている日は波をかぶって流されそうになるし、機械に巻き込まれれば大ケガをしてしまう。高い集中力ととっさの判断力が求められる仕事です」
大畠さんは建設作業員などの仕事を経て、この佐々波鰤網に入社。お父様や叔父様も同じ会社で船頭をしており、子どもの頃からその姿に憧れを抱いていた大畠さんは、23歳で漁師に転身します。
「漁師というのは、大体朝の4時頃に出港し、お昼くらいに帰ってくるという仕事です。慣れない内はこれが本当にキツい。しかも、魚は毎年安定的に取れるわけではなく、水揚げ量の少ない年は給料にも響きます。そんな厳しさがある一方で、大漁のときには他に代え難い喜びがあります。特にブリの大漁は格別ですよ(笑)」
七尾生まれ七尾育ちの大畠さんは、私と同い年で、実は小学生時代からの古い友人です。地元のコミュニティを大切にし、休日は仲間とゴルフを楽しむ。そんな姿からは、地元に根を張って生きることの豊かさを教えてもらったような気がします。

今や漁師も“ビジネスマン”!?

漁師の仕事は命の危険と隣り合わせですが、荒々しい船上のイメージとは打って変わって、港にある佐々波鰤網の事務所は非常に整理が行き届いた空間になっています。失礼な言い方かもしれませんが、これはとても意外な光景でした。
「確かに漁師というと“荒くれ者”のイメージがあり、事務所も雑然とした場所を想像されるかもしれません。しかし、これは社長の哲学なのですが、ウチの会社では業界のイメージアップを図るべく、作業環境の改善や安全対策、社員の教育や健康維持などに力を注いでいます」
事務所には、図書館のように整理された本棚があり、社員のみなさんは日々勉強に励んでいます。また大畠さん自身も、安全委員会を組織して危険なポイントの発見や改善に務めているとか。
「もはや魚を捕っていれば食えるという時代ではありません。情報収集して経済の流れをつかまなきゃいけないし、職場でのコミュニケーションを大切にしないと若い連中だってついてこない。そういう意味では、漁師もビジネスマンと何ら変わりないと思います」
佐々波鰤網の港には、とてもおもしろい光景が並んでいます。何と防波堤をキャンパスに数多くの名画が描かれているのです。実は、これも改善の取り組みのひとつだとか。
「港って、鳥がたくさん飛んでいて、魚臭くて汚いというイメージがあるじゃないですか。それを改善するべく、金沢美術工芸大学の学生さんに依頼し、防波堤に絵を描いてもらっています。景観を変えることで、港を人の集まる場所にしていけたらなと思っています」
大海原をバックに絵画を鑑賞できるなんて、世界でも珍しい場所かもしれません。デートなどにもオススメのスポットです。

“顔の見える漁業”で6次産業化を進める

「今の時代、正直言って漁業を取り巻く環境はどんどん厳しくなっています。魚の単価は下がっているし、若い人の“魚離れ”は進む一方です。そういった中で、漁師として何ができるのか。常に危機感を持って仕事をしています」
そんな状況に対峙するべく、佐々波鰤網では様々な取り組みを行っているとか。そのひとつが、魚の直接販売。七尾で人気の朝市です。
「毎月一回、さざなみ漁港で直接販売を行っています。ここに並ぶのは、水揚げ直後の新鮮な魚ばかり。これらを『さざなみ鰤』や『さざなみ魚』と呼び、品質に絶対の自信を持つ“ブランド魚”として打ち出しています」
この鮮度を支えるのが「海水のシャーベット」という技術だとか。魚の鮮度を保つには、とにかく冷やすことが大事だそうですが、一方で冷やしすぎると凍ってしまい、体が曲がってしまうなど品質が落ちてしまうとか。魚ごとの適温に合わせて体をまんべんなく冷やし、なおかつ海水にいるときの塩分濃度を損なわない海水のシャーベットは、まさにブランド魚の品質を保つ秘密兵器と言えます。
「そういう技術の進歩もあり、鮮度を保ったまま東京へ運ぶことも可能になりました。そこで、新しい試みのひとつとして、池袋の西武百貨店で直売会も行いました。漁師が自ら消費者の手に魚を届けるというのは、いわゆる『6次産業』と呼ばれる取り組みです。生産者が自らおもむき、漁法や魚の説明をした上で買ってもらう。これは食の安全にもつながる大事な取り組みなので、今後とも継続していきたいと思っています」
新鮮な魚を、漁師さんから直接買う。消費者にとって、これはとても贅沢な行為です。このように、生産の履歴を示しながら販売まで行うというのは、“顔の見える漁業”ともいうべき新しい形のように思います。

能登のイカはなぜ透明なのか?

脂の乗りきった寒ブリは、刺身にしてもよし、ブリしゃぶにしてもよしという、冬の食卓を彩る風物詩と言えます。特に、沖から2〜3キロという距離で行っている定置網漁のブリは、捕れてから市場に並ぶまで何と2時間程度という驚きの鮮度。「さざなみ鰤」が“ブランド魚”たるゆえんです。
「魚はとても繊細で、少しでもストレスを感じると魚肉の旨み成分が分解され、鮮度が落ちてしまいます。それを防ぐため、捕ったらすぐに海水シャーベットで締め、鮮度管理を徹底します。また、七尾の海は暖かい対馬海流と寒いリマン海流が交差し、良質のプランクトンが大量に発生する場所でもあります。その栄養満点の海水もおいしさの秘訣ですね」
このように、豊かな自然環境のおかげでおいしい食べ物に恵まれていることが能登の自慢と言えます。しかし、大畠さんはここに警鐘を鳴らします。
「能登の人は、食に関して贅沢だと思うんですよ。例えば『イカは透明なもの』だと当たり前のように思っていますが、外の人の常識では『イカ=白』ですよね。透明なのは新鮮な証拠。そういうことに、ちょっと無自覚だと思うんです。能登は米も野菜も肉も酒もすべてがおいしい。正直、北海道にだって負けないと思っています。でも、地元の人がその魅力に気づいていないと、対外的にPRだってできません。食で勝負するためにも、まずは地元の人が地元の食材についてよく知ることから始めるべきだと思います」
大畠さんのこの言葉には、同じ能登人として、私も背筋が伸びる思いでした…。豊かな自然の恵みを当たり前のことと思わず、ありがたく享受しながら外の人にもお裾分けしていく──。近い将来、多田屋でも「さざなみ魚」とのコラボレーション企画をやってみたいと思います。

大畠さんプロフィール
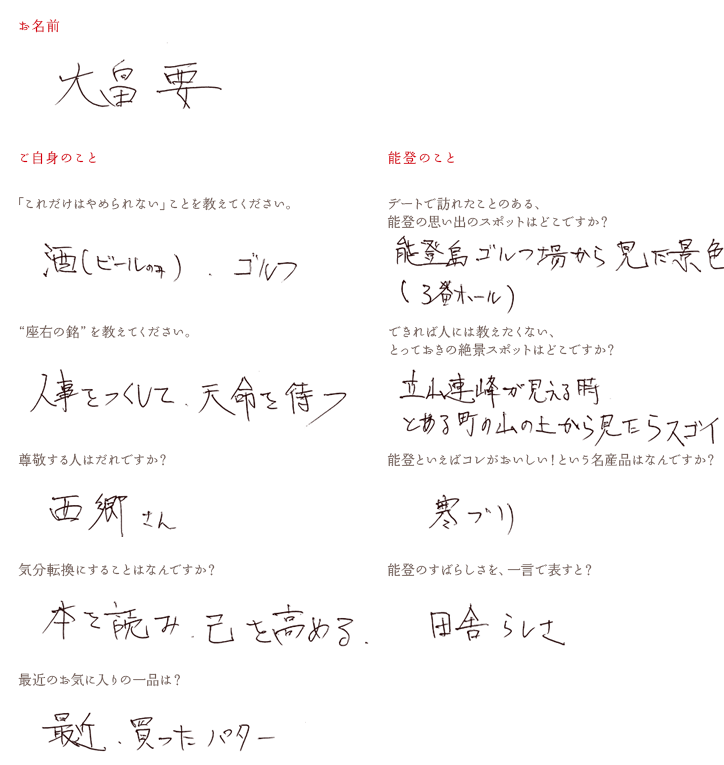

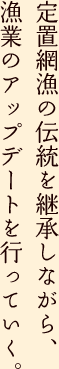






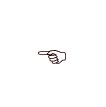
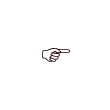

自分と同じ歳の大畠さん。友人でもある彼と能登の事、そして仕事の事をこれだけがっちりと話したのは初めて。能登が本当に好きな気持ちが伝わってくる。そんな彼が選んだ定置網漁という仕事。彼の能登への愛が形になったような漁のスタイルだ。しかし、その漁はまさに命がけ。自分の命だけでなく、副船長は沢山の命を預かる。一緒に船に乗ってみて、初めて見るその真剣な眼差しに、もっとブリを感謝して食べようと思った。