『能登』編集長
経塚 幸夫さん(つねづか ゆきおさん)
“地産地消文化情報誌”を標榜し、
丹念な取材と洗練されたデザインで地元の情報を発信する雑誌『能登』。
グルメ情報や観光ガイドにとどまらず、その奥にある人々の想いや
農林漁業が抱える課題にまで目を向けた能登の“総合誌”です。
そんな『能登』を発行する経塚幸夫さんの編集哲学に、
多田健太郎が迫りました!
『能登』の編集長は金沢出身の住職!?

『能登』はその名が示す通り、テーマを能登にしぼり込んだ珍しい雑誌といえます。「能登で丸一冊」というものは市販の観光ガイドにもなく、大抵は「金沢」エリアに付随する程度の扱い。この出版不況の時代にあって、なぜ“能登”という1テーマで雑誌を作ろうと思ったのでしょうか。
「理由のひとつは、前職の新聞記者時代にあります。私は30年間、北國新聞に勤めていたのですが、入社後に3年間ほど穴水支局の勤務になり、『夢半島のとキャンペーン』という仕事に携わって能登中をまわりました。そこでこの土地の魅力に触れ、『いつか能登をテーマにした本を作りたい』という想いを抱くようになりました」
もうひとつの理由は、子どもの頃から積み重なってきた“縁”だとか。経塚さんは金沢のご出身ですが、お母様が能登の方で、小学生の時から夏休みはその田舎で過ごしていたそうです。さらに、20歳の時には初めて見たキリコ祭りの迫力に魅せられ、やがて能登の女性と結婚をも果たします。そうやってこの土地との縁が深まり、「最終的には能登で何かをしたい」という気持ちが募っていったとか。
「妻が能登の門前町にあるお寺の娘で、先代が亡くなった際、私が住職を継ぐことになり、能登で暮らすことになりました。これをきっかけに、『能登』の創刊に着手。雑誌というメディアを選んだのは、能登の情報をじっくりと、かつ幅広く伝えるためには、書籍やウェブよりも適していると考えたからです」
こうして、能登を1テーマにした初の雑誌が誕生しました。それは、経塚さんが長年温めてきた能登への想いが動き始めた瞬間でもありました。

“お金を取らない”というこだわりのルールとは?

能登という1テーマで雑誌を作ることには、当然ながらリスクも伴います。テーマをしぼり込むということは、それだけ読者や取材対象を狭めることにもつながるからです。しかし経塚さんは、様々な“こだわり”によってこの課題を乗り越えていきます。
「まずひとつは、『人に焦点を当てる』という点です。例えばグルメの情報にしても、作り手の想いを知ることで、味わいはより一層深くなるはず。人の取材が『能登』の基本ですね」
また、雑誌というのは売り上げと広告収入によって成り立っていますが、その広告集めに関しても、経塚さんは強いこだわりを持っているとか。
「取材対象からお金を取らないというルールを設けています。お金を出したお店しか掲載しないとなると、雑誌ってダメになるんですよ。だから、載せるお店はすべて自分で食べて、自分の責任で選びます。しっかり掲載のラインを引き、東京や金沢からでも人を呼びたいと思えるお店だけを厳選し、クオリティを保つ。どんなに経営が苦しくても、ここだけは守ります」
能登という限られた範囲の中で、取り扱う情報をさらに厳選し、人々に深くコミットしながら取材を進めていく。そして、自信を持って発信できる濃度の高い情報を掲載することで、能登の人間以外でも楽しめる“普遍性”を獲得する──。『能登』はまさに、“地域密着型”雑誌のお手本といえるのではないでしょうか。

92歳の読者から届いた手紙の意味

販売数の約半分が地元で占められるという『能登』は、ここに暮らす我々にとっても重要な役割を果たしています。というのも、能登の人間には「自分が住んでいる地域以外のことをあまり知らない」という傾向があり…そこでひと役買ってくれるのがこの雑誌です。
「もっと地元の人たちに能登の魅力を知ってもらい、例えば休みの日に門前でお蕎麦を食べたり、和倉温泉で一泊したりと、地域の中でお金を落とし合う動きを活発にできたらなと思っています。これからますます人口は減っていきます。外から人を連れてくることばかりを考えても、経済はなかなか活性化していきませんからね」
そこでポイントになるのが、エリアや世代を超えた“人と人とのつながり”だとか。
「能登には今、若い人たちが始めたおもしろいお店がたくさんあります。羽咋の<a href=\"/nototsuduri/2011/fallwinter/shop/details/1/\" target=\"_blank\">『神音カフェ』</a>や七尾の<a href=\"/nototsuduri/2011/spring/shop/details/3/\" target=\"_blank\">『歩らり』</a>などはその代表格。こういった動きを紹介し、“会いに行きたい人”を増やすことは、地域経済の活性化にも役立つと考えています」
能登でおもしろい活動をしている人たちを紹介し、その交流をうながす。これは、この土地に幅広い人脈を持つ経塚さんならではの仕事だと思います。
「これは私が金沢出身の人間ということが大きいかもしれません。つまり、偏ることなく“オール能登”の視点で眺められるバランス感覚が生きているのではないか。こないだも、92歳のおじいちゃんから『こんな雑誌が出てうれしい。今後も続けてください』と励ましのお便りをいただきました。エリアや世代を超え、能登を活性化させていけたらと思っています」

能登の高校生に選択肢を与えたい

「この土地に昔から住んでいる人には、『能登は何もないところ』と思っている人が多いんですよ。もしもそういう大人に囲まれて育ったら、能登の子どもたちだって同じように感じてしまうはずですよね。そうなると、彼らにとって能登は『高校を卒業したら出て行くところ』になってしまう。僕としては、そこを変えたいなという想いがあります」
能登に可能性を感じ、新たな仕事を作り出している若い世代の活動を積極的に取り上げている背景には、そんな想いがあるのだとか。
「とにかく、地元の高校生が能登に目を向けるきっかけを作ることが大事ですよね。世界農業遺産に指定されたことを一時のブームで終わらせてはいけないし、若い世代のクリエイティブな活動を伝えることで能登が刺激的な場所であることを知って欲しい。『能登』という雑誌だって、高校生に『能登でもこんな本格的なものが作れるんだ!』と感じてもらいたいからこそ、お金と労力を惜しまずに取り組めているのだと思います」
今はネットも普及し、能登で暮らすことの不利は少なくなっています。環境がよく、食も豊かな能登は、これからの若い世代にとって魅力的な土地に映るのではないでしょうか。
「そのためにも、この雑誌が“職業ガイド”のような役割を果たせたらなと考えています。『能登に残る』という選択肢を与えるためにも、また、一度外に出た若者が戻ってくるときのためにも、受け皿としての雇用整備は必須ですよね。なので、これからも能登の様々な仕事を紹介していきたいと思っています」

奇跡的な“丁度よさ”という資源

能登の魅力を深く理解し、雑誌まで創刊してしまった経塚さんですが、元々は「日本で能登が一番いいところ」と思っていたわけではなかったとか。
「私は取材をするという仕事柄、ほとんどの都道府県に行きましたが、九州には雄大な海があり、東北には深い森がありました。能登は自然の豊かなところですが、そういうものすごい自然に比べると、ここが一番だとは思えなかったんです」
ところがここ数年、「やはり能登が日本一なのでは?」という気持ちが強くなってきたそうです。ポイントは、能登が持つ“丁度よさ”だとか。
「確かに『これが一番』というものはありませんが、穏やかな気候に住みやすい地形、都市に近い立地や豊富な食べ物など、能登は人間が暮らすにはすべてが丁度いい。ここが大きな魅力です。能登の自然は“大自然”ではなく、里山や里海、つまりは“人の手が入っている自然”です。人間が自然から恵みをいただくという営みが古来より続いており、農林漁業とそれに伴う生活文化、祭りなども含め、すべてがひとつの『生活システム』として機能している。世界農業遺産に指定されたのも、それが生きているからだと思います」
奇跡的な“丁度よさ”という資源──。これは能登に暮らす人間にとって、とてもありがたく、同時に強く誇れる部分です。
「今は原発事故の影響もあり、東京にこれだけ人が集中していいのか、エネルギーをひたすら消費していくだけの社会でいいのか、そんな疑問がうずまいている時代ですよね。そんな今こそ、能登の魅力をしっかり訴えていくべきではないかと感じています。それを勉強するための時間はいくらあっても足りませんね。一応、本業はお寺の住職なので…(笑)。これからも、そちらを疎かにせず、『能登』に全力を注いでいきたいと思います」





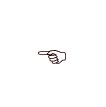
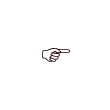

能登の魅力を発信できるのは、能登以外に住んでいた人かもしれない。しかし、発信するには能登に住まなくちゃならない。経塚さんはその両方を持ちながら、能登の素晴らしさを絶妙のバランスで伝えてくれる。この雑誌「能登」は単なる情報誌ではない。経塚さんが伝えようとしているのは、能登で育った方々の誇りであり、これから社会に出て行く若い世代への生き方の提案だと思う。本当にありがとう。